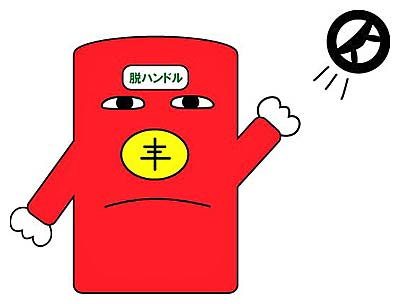会員など総勢590人が集まった
会員など総勢590人が集まった
日本政府観光局(JNTO、松山良一理事長)は1月31日、東京都内で「第10回JNTOインバウンド旅行振興フォーラム」を開き、重点地域の海外事務所長らが、各地域での訪日旅行に対するニーズなどを報告する市場説明会と個別相談会を行った。JNTOは訪日外客数1千万人を目指し、質の向上と量の拡大を掲げ、伸びが期待されるASEANは富裕層と中間層の取り込みを狙う。フォーラムには会員の旅行会社や宿泊施設、賛助団体の自治体など約590人が参加。各市場の動向を紹介する。
【内川 久季、伊集院 悟】
◇
 松山良一理事長
松山良一理事長
松山理事長はフォーラム冒頭、「2012年の訪日外客数は836万8千人となり、年別では10年に次ぐ2番目。全体的に、震災の影響からほぼ回復した」との見方を示し、「市場別では、中国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、インドが過去最高を記録。LCCの就航や航空運賃の低下、クルージング、ビザ発給の緩和などが追い風になった」と振り返った。13年については、「今年は日本ASEAN協力40周年、日本ベトナム友好年、日豪観光交流年。質、量の両面で訪日外客数を増やし、1千万人達成を目指す」と強調。「海外での日本のイメージは、イタリアと並ぶぐらい良い。今後は、日本へ行きたいと思わせる整備が大切だ」と述べた。
13年のJNTOの取り組みは、(1)質の向上と量(裾野)の拡大(2)訪日旅行への受け入れ体制の整備促進(3)MICE誘致の拡充強化――の3点を挙げた。
「質の向上と量(裾野)の拡大」では、ASEANの中間層が顕著に伸びており、今年はジャカルタ事務所を開設。富裕層と中間層の取り込みとリピーターの確保、教育旅行の強化を行う。量の拡大は、とくに中国、韓国、台湾に注力する。
「訪日旅行への受け入れ体制の整備促進」は、Wi―Fiの完備と、海外クレジットカードの使用可能場所の拡大を訴求した。「MICE誘致の拡充強化」は、シンガポールやソウルに奪われている国際会議やインセンティブ旅行を、日本へ戻すための誘致強化を積極的に行う。
□■□■
各市場の動向は次の通り。
タイの12年訪日数は3月を除く各月で単月として過去最高を記録。バンコク事務所の益田浩所長は「現在の韓国、台湾、中国、アメリカ、香港の5大市場のなかに、6大市場として入ることが目標」と話した。日本の人気がとても高く、訪日人数が多い月は4、10、3月の順で、桜人気を強調。高額支出を控えるため、欧州などの遠方よりもアジアツアーの人気が高く、昨年からマルチビザも導入されFIT化が進み、旅行形態が個人旅行化している。益田所長は「今後は、オンラインの事業者も増えるだろう」と予測。「タイには春夏秋冬の感覚がないので、何月なのか明確に説明する必要がある」などセミナーでのポイントをアドバイスした。
シンガポール市場は、放射能への懸念が根強く残り、とくに東京は厳しい状況が続いている。シンガポール事務所の足立基成所長は、今までのターゲット層だった富裕家族層からの「5年は放射能が心配で日本へ行けない」「子供や孫を連れて行くことはできない」「日本に行くと妊娠に影響がでるという噂がある」という声を紹介し、「シンガポールは、衛生管理が行き届き、綺麗で整備された街なので放射能の問題はとても大きい」と述べた。このため、13年はターゲットを富裕層からミドル家族層へシフト。また、約8割がFITである現況を踏まえ、個人旅行比率の増加、とくに若者層へ注力していく方針だ。
マレーシア市場は、12年9月からマルチビザの申請受付を開始し、FIT層の需要も伸長。足立所長は「ターゲット層の中華系富裕層、中間層に加え、ムスリムのマレー系にも訪日の関心が高く日本からマレーシアへの修学旅行が増え、学校交流も盛んになった」と報告した。JNTOはマレーシア旅行業協会(MATTA)と連携し、ムスリムに対しての理解度を高め、より一層の訪日促進活動を行うという。ムスリムツアーの誘致は、魅力的な観光素材とハラルフード、お祈りへの対応の重要性を強調した。
インドネシア市場は、親日家が多く、訪日旅行は堅調に拡大。親戚を含めた20―30人の家族旅行が主流で、日本でのショッピングやテーマパークが目的という。足立所長は懸念材料として「近年は韓国の露出が高く、日本よりも目立っている。いかに露出できるか、目立てるかがカギ」と語った。アッパーミドル層の増大が顕著で、外国旅行の需要は2015年に4千万人、20年に8千万人になる巨大なマーケット。マレーシアと同じく、中華系に加え、ムスリムマーケットの加速も見られる。さらに、若者はLCCでの訪日が増え始め、今後は富裕層だけではなく幅広い訪日促進活動をしていくという。
ASEAN市場ではインドネシアに最も注目しており、今年の5月にはジャカルタ事務所を開設予定だ。経済発展にともない、外国旅行がレジャーとして定着。足立所長は「ムスリムは2億人市場といわれ、いまだ開拓されていない市場。信頼を得て、今後この市場の開拓をしていく」とし、東南アジアからの訪日を69万人から100万人に拡大する目標を示した。
韓国市場についてソウル事務所の鄭然凡所長は、「放射能による風評被害や竹島問題の影響からは回復してきた」とし、13年は日韓の地理的な近接性を活かした1泊や2泊の短期旅行の需要拡大を狙う。5日間で周遊できる北海道プランは依然として人気が高く、近年ヒーリングブームが起こり訪日旅行に盛り込まれることが増えたという。また、昨年秋田県が誘致した韓国ドラマを事例にあげ、今年も東北需要促進をはかるとした。
台湾市場は、震災時210億円も義援金が集まるほど親日家が多く、訪日客の7割以上がリピーター。航空便増加で、とくに首都圏・関西圏への個人旅行が増加している。震災後は、格安ツアーの乱売で中間価格が売れづらい状況だが、富裕者層の高級ツアーの売れ行きは好調。また、訪日促進の最も重要ポイントとして、日本交流協会台北事務所経済室の山田敬也主任は「インターネット環境の整備」を挙げ、「台湾人はネット好き。Wi―Fi、無線LANの整備をし、ロビーと部屋で使える環境作りが必要」と説明。フェイスブックの普及率も日本より高く、ネット利用者の8割が利用し、旅行中に画像や日記を公開できるかを気にするという。
中国市場は、引き続き高い成長が期待され、海外旅行者数は増大する見込み。12年には2千万人を超えるとされ、15年には8300万人と予測した。北京事務所の飯嶋康弘所長は「旅行会社は新聞と違い政府管理がなく自由に動けるので、もっと訪日プロモーションをしてほしい」と訴えた。
上海市場は、中国全体の団体旅行中4割を上海が占め、最も多い送客数を誇っていたが、尖閣問題の影響を受け3―8割減となっている。MICE誘致やインセンティブ旅行の強化を訴え、上海事務所の小沼英悟所長は「MICEは観光旅行のオフシーズンの秋に需要が高まる」と説明。人気のアクティビティは雪合戦で、「ツアーには中国語が話せるスタッフ・ランドオペレーターが必要」と強調した。
香港市場は、13年の訪日客数が60万人の壁を突破すると見込む。海外旅行需要は韓国から日本へシフト。香港事務所の平田真幸所長は「中国と香港は別に考えるべき。政治的な理由で日本観光が減少することはないが、放射能がネック。最近は東京への観光が戻ってきている」と報告した。