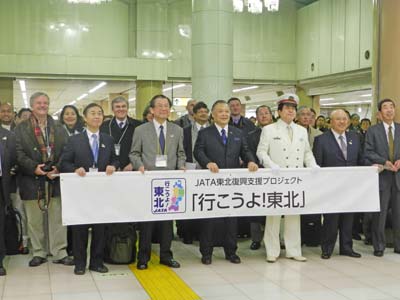観光庁は11月30日、旅行会社アミューズトラベルが2009年に起こした北海道トムラウシ山のツアー登山での遭難事故後の国の対応の検証をまとめ、中間発表を行った。同社への計8回におよぶ立入検査がすべて事前連絡のものであることや、業務停止処分後の対応について規定がなく、処分後は2回の事前連絡による立入検査でチェックを終えていたことが判明。観光庁の対応の甘さを露呈した。今後、抜き打ちの立入検査の実施や、処分後の対応の規定を作ることを検討していく方針という。
【伊集院 悟】
◇
≪観光庁、処分後の対応の規定づくり≫
今年11月3日に中国の万里の長城付近で日本人3人が死亡する事故が起きたツアーを実施したアミューズトラベルは、09年にも北海道トムラウシ山のツアー登山で8人が死亡する遭難事故を起こしている。羽田雄一郎国土交通大臣は11月8日、今後の同社への立入検査、処分を含む旅行業者全体に対する指導監督の改善につなげるため、観光庁内に観光庁長官をトップとする検証のためのチームを設置し、検証するよう指示。検証チームでは09年7月―11年12月までに在職した観光庁幹部や管理職、担当者計14人にこの間の対応に関しヒアリングなどを行い、中間報告をまとめて11月30日に発表。同日、観光庁総務課の河野春彦課長が会見を開いた。
◇
09年7月16日の事故発生後、7月31日と10月6日の2回の聴取をはさみ、第1回の立入検査が行われたのは11月5日。立入検査が遅れた理由に(1)まずは聴取という手段をとったこと(2)警察の捜査が行われていたこと(3)日本山岳ガイド協会の「トムラウシ山遭難事故調査特別委員会」が設置され、その状況を注視していたこと(4)ツアー登山の専門家の知見を集めて全体的な対応を行うべく、有識者からなる「ツアー登山安全対策連絡会議」の準備をしつつ、立入検査でチェックすべき項目の精査を行っていたこと――などを挙げた。
10年3月31日、「旅行業者が行うツアー登山の安全確保」を取りまとめ、旅行業協会とアミューズトラベルへ指導文書を通達し、「ツアー登山運行ガイドライン」の遵守、ツアー登山の企画内容・実施体制・管理体制などの総点検と確認をするよう促した。6月10日、22日に同社の安全対策について同社社長から聴取。7月から10月にかけての4度の立入検査を経て、12月15日、旅行業務に関する管理・監督義務の違反などを理由に51日間の業務停止処分を行った。
3月8日、法律違反がないことから、法定の拒否事由がないとして同社の旅行業の登録更新については認め、6月30日と12月12日の立入検査をもち、同社への検査・監督を終えている。
◇
河野課長は事故後の対応について、「8回の立入検査や指導・処分などについては、法例に則って行ったので職務をまっとうしている」としたうえで、「結果的に、その後に遭難事故を起こしているので、不十分な点があったことも事実」とする見解を述べた。
鉄道局など、他庁や他局では検査専門の職員を確保しているが、観光庁の場合は、他の業務も行いながら旅行業の指導・監督に従事する要員として本庁17人、地方運輸局71人だけで対応。観光庁長官登録の第1種旅行業者(12年4月時点で726社)については、立入検査は平均すると約10年に1回だけとなる。また、問題を起こしたり処分された会社への対応について規定がなく、処分後の同社への立入検査も、規定ではなく自主的な判断という。さらに、立入検査はすべて事前通告で、抜き打ち検査は一度も行っていない。
河野課長は観光庁の見解として、今後について「抜き打ち検査の実施や、処分後の対応の規定を作ることを検討していく方針」と話す。同社への指導に関しては、会社側が提出した書面へのチェックや、提出のあったツアーのみをサンプリングチェックするに留まり、同庁からの積極的な監督は行っておらず、またそれを義務付ける規定もないのが現状だ。
今後の改善策について既出の「抜き打ち検査の実施」や「処分後の対応の規定作り」に加え、(1)処分の厳罰化(2)検査方法の改善(3)処分後の立入検査の継続的かつ頻度を高めての実施(4)組織的な安全のマネジメントなど安全管理体制の確立(5)重大事案の処理では、全体の方針だけでなく、個別具体的な対応についても観光庁幹部がみずから能動的に指揮を取ること――などを挙げている。
なお、最終報告は年内をめどに出される予定だが、基本的にはこの中間報告がベースになるという。