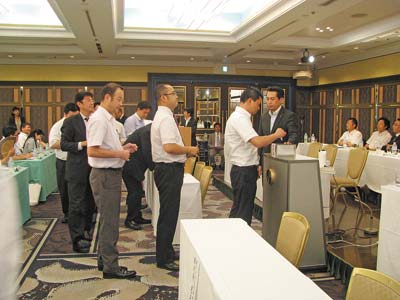次期青年部長に選任された
次期青年部長に選任された
山口敦史氏
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の青年部(横山公大部長、1460会員)は7月18日、東京都内のホテルで臨時総会を開き、第21代青年部長に、現・研修部担当副部長の山口敦史氏(山形県天童温泉・ほほえみの宿 滝の湯専務)を選任した。史上初の選挙となった前回の青年部長選挙に続いて今回も山口氏と、現・監事の山本剛史氏(群馬県草津温泉・ホテルニュー高松代表取締役)の2人が立候補。各都道府県部長47人による投票、即日開票により、25票対22票の僅差で山口氏が次期青年部長となった。
【増田 剛】
◇
青年部長を決める選挙は現部長の横山公大氏と、政策担当副部長の森晃氏が競った前回に続いて2回目となった。5月26日から6月1日までの受付期間に立候補したのは、山口敦史氏と山本剛史氏の2人。
横山部長は冒頭、「山口候補、山本候補ともに未来のことを熱く語り合っていた。次期も大変な2年間になると思うが、どちらに託しても素晴らしい青年部に向けて牽引してくれるだろうと思う」と激励。来賓として17代部長の佐久間克文氏、18代部長の永山久徳氏、19代部長の井上善博氏も両候補にエールを送った。
 横山部長(左)と握手する山口次期部長
横山部長(左)と握手する山口次期部長
臨時総会では、立候補受け付け順に山口氏、山本氏の順で15分間の最終演説を行った。
 演説する山本氏
演説する山本氏
山口氏は「未来を変える三本の矢」として(1)組織力の強化(2)魅力ある事業の創出(3)災害支援ネットワークの構築――を挙げた。魅力ある事業の創出では、旅とスポーツ、ファッション、健康など異業種とのコラボレーション事業などにも取り組みたいとし、「明るい未来のために変わり続けよう」と呼び掛けた。
一方の山本氏は温泉枯渇につながる地熱発電に反対する姿勢を打ち出し、「地熱発電対策協議会の立ち上げ」を提案。さらに数字に強い経営者の育成や、食材リベート防止の研究などの必要性を強調し、最後に「自発的な青年部組織へ」と訴えた。
その後、全国47都道府県の部長による投票と、開票により、山口氏が25票、山本氏が22票と僅差で山口氏が第21代青年部長に選任された。
◇
山口 敦史氏(やまぐち・あつし) 1971年生まれ。40歳。94年専修大学経営学部経営学科卒業後、滝の湯ホテル入社。現在、ほほえみの宿 滝の湯専務取締役。
【青年部経歴】1999―2000年度に全旅連青年部情報ネットワーク委員会委員、07―08年度に山形県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部部長、09―10年度に全旅連青年部観光まちづくり探究委員会委員長、11―12年度に全旅連青年部研修担当副部長。
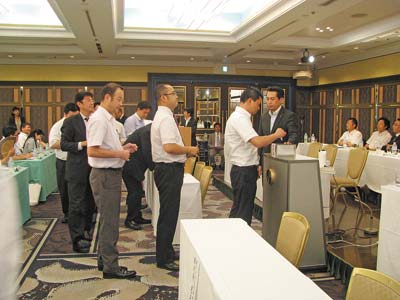 投票する都道府県部長
投票する都道府県部長
≪懇親会で多数の議員と意見交換≫
臨時総会終了後の懇親パーティーには、観光振興議員連盟会長の川内博史氏、元首相の鳩山由紀夫氏ら多数の国会議員が出席し、当日午前中に行った消費税の総額表示反対などの陳情活動に続き、地元選出議員と青年部員が意見交換を行った。
 鳩山由紀夫氏
鳩山由紀夫氏  川内博史氏
川内博史氏