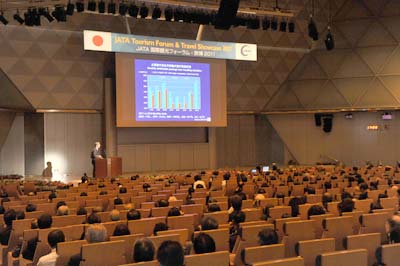旅館の魅力は土地の魅力、宿文化を語る会

旅行作家で現代旅行研究所代表の野口冬人氏が会長を務め、旅館の若手経営者や経営者候補など旅館業界の次世代を担う若手メンバーが今後の旅館業界や理想の宿像などについて語り合う「宿文化を語る会」の第2回会合が8月28日に「助六の宿 貞千代」(東京・浅草)で開かれ、自身が経営したい将来の宿像をテーマに話し合った。
オブザーバーとして参加した貞千代の宿のご主人・望月友彦氏は、貞千代の現在のスタイルについて「交通の便が良く駅から近ければ、ビジネスホテルの方が経営し易かったが、ここは駅から距離があるので観光旅館にした。観光旅館の魅力は、その土地その土地の魅力を味わえることだと思うので、貞千代は江戸の町衆の雰囲気を前面に出した」と語った。
「日本の宿 古窯」専務で「悠湯の郷ゆさ」を経営する佐藤太一氏は古窯とゆさのターゲット層や価格帯の違いを紹介。将来の宿像としては「10室くらいの自分だけで見きれる小さい旅館」をあげ、「大きい旅館はマーケットインの手法を使い多くのニーズを意識せざるを得ない。それとは対照的に、小さい旅館ならプロダクトアウトで宿の個性を出しそのコンセプトに合う客だけを迎えることができる。将来の夢としては現在の2旅館に加え、10室くらいの小さい旅館をやってみたい。シュミレーションしているが、オペレーションの仕方によっては10室でも黒字を出せる」と自信をのぞかせた。
「雀のお宿 磯部館」社長の櫻井太作氏は宿の将来像として「日本人に分かるキメの細かいサービス」をあげた。「今は、学生や医者、薬業界などの会議や研修、法事など、どちらかというとニッチなニーズの団体を拾っているが、将来の夢としては、日本人に分かるキメ細かいサービスが売りの宿をやりたい。日本人のキメの細かさは世界一だと思う」と語った。
旅行作家で現代旅行研究所専務の竹村節子氏の「日本旅館は何がベースか」の問いに、「ホテル 対滝閣」常務兼若女将の大澤昌枝氏は「日本文化や伝統の継承」をあげる。宿の将来像については「親のやってきた伝統を継承したい。日本文化をしっかりと繋いでいくことが一番大切」と語る。ただほかのメンバー同様に「自分の見える範囲の小さい旅館もやってみたい」との夢も抱く。
そのほか、竹村氏からは外国資本が旅館を買い占める現状について、野口氏からはリタイア後の男性1人旅の増加や、連泊と何カ月にもおよぶ住みつきの違いなどについて提起され、参加者全員で意見交換。また、クレーム後の社員へのフィードバックや困った客への対応など、同業者だからこそ分かる悩みや迷い事について熱く意見が交わされた。
なお、第3回の会合は来年1月下旬か2月上旬を予定。参加希望者は旅行新聞新社内にある「宿文化を語る会」事務局まで。電話:03(3834)2718。