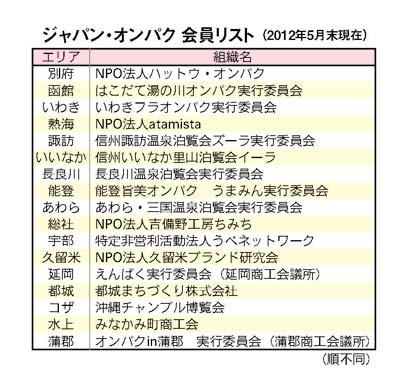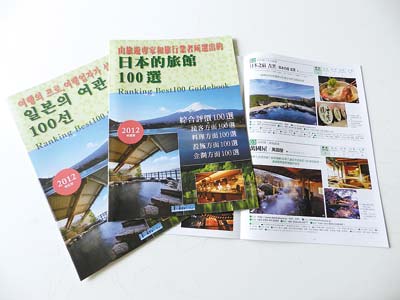小笠原村観光局
小笠原村観光局
主任 根岸 康弘氏
小笠原諸島が昨年、ユネスコ世界自然遺産に登録されてから1年が経った。世界遺産登録後に出てくるのが、屋久島などに代表される、観光客急増による環境破壊の問題だ。観光振興と自然環境保護、一見相反する2つの取り組みのバランスをどう取るべきか。登録から1年を経た小笠原諸島の観光の現状と自然環境保全の取り組みを、小笠原村観光局の根岸康弘主任にうかがった。
【伊集院 悟】
◇
≪自主ルールで自然環境の保全≫
世界遺産登録前の小笠原は、観光客数が年1万2、3千人くらいで、若者層やリピーターなどが多く、ダイビングやホエールウォッチングなど目的性の高い人がほとんどでした。
自然環境の保全については、世界自然遺産登録を目指す前からすでに意識を高く持ち実跡しており、幹はできていたので、登録前後に慌てることはなかったです。エコツーリズムという言葉がまだなかった1988年のホエールウォッチング開始時から、持続可能な利用に取り組みました。ホエールウォッチングに関しては、国内での統一ルールなどはないので、野生のクジラにストレスを与えないように、一度にアプローチできる船の数や、船がクジラに近づける距離を制限するなど、自主ルールを決めています。
固有種を守るために、山へ入る際には外来種の種子や動物を持ちこまないよう靴底洗浄を徹底しています。また、登録前後から、島民の意識もそれまで以上に非常に高くなっています。小笠原は移住者が多い島。島を気に入って移住してきて、後世にもこの宝を残したいという思いが強い。ビーチなどは、島民による自主的な活動によって常にキレイに保たれています。
登録後は、定期船での観光客はこれまでの1・7倍。400―500人乗れるクルーズ船での入島も含めると2倍ぐらいになります。閑散期に増えたことや、クルーズ船客はあまり森へ深入りしないことから、心配される自然破壊は起きていません。小笠原の場合は、他の世界遺産地と違い、ボトルネックが細い。入島は基本的には6日に1便の定期船によるもので、今後も便数が増える予定はないので、観光客数は物理的に絞られてきます。
また、入島方法も船からだけなので、管理がしやすい。今では靴底洗浄を入島、入林時だけでなく、竹芝桟橋の乗船時点で行うなど、より徹底させています。
登録後はトレッキング目的の観光客も増えました。冬のシーズンは日本列島の多くの山は閉山しますが、小笠原はトレッキングに最も適した季節なので、それを目的とした方達が小笠原に来られています。通常、トレッキングシューズは何足も持っているものではないので、前の週に別の山に登られた方が、その山の種子などを靴底につけたまま小笠原に来られることもあります。
環境保全において一番重要なことは、観光客に取り組みを知ってもらうことです。観光客の協力なしには自然環境の保全はできません。協力してもらうために、取り組みの意義を意識してもらえるよう、靴底洗浄などを実施しています。
≪観光客の質が変化、旅行会社へ丁寧なレクチャーを≫
登録後の観光客の動向は、量の増加にくわえ、質の変化も見られます。それまでのダイビングやホエールウォッチング目的のお客様に加え、中高年のトレッキング客や、小笠原に来るというよりは「世界遺産の島」に来るという物見遊山的な添乗員つきのツアーが増えました。これによるミスマッチが起きているのが現在の課題です。
添乗員つきのツアーはこれまでほとんどなかったので、添乗員の方も小笠原のことをよく知りません。また、トレッキングのお客様は「○○山に登る」などある程度行程や山の特徴を頭に入れて来られるので、ギャップやミスマッチが起きにくいのですが、物見遊山的なお客様の場合は、小笠原諸島がどういう所なのかということを知らずに来られる場合が多いです。島に来た時点で半分目的を達成し、初めて観光協会の窓をたたき、「小笠原では何ができますか」と尋ねられる方もいらっしゃるようです。
とくに多いのが、「小笠原=南の島=リゾート」という思い込み。リゾートをイメージして来られるお客様も多いですが、実際の小笠原はリゾートとはかけ離れています。父島の南西にある「南島」という無人島は絵的にキレイなので、多くのメディアで使われますが、写真や映像は一部を映しているだけなので、誤解されやすいです。多くのお客様が抱くイメージは「大きな遊覧船で行って桟橋に降りる」というもので、ハイヒールを履いた方や杖をついた方が来られたりもします。しかし、南島の現実は、桟橋などの人工物は一切なく、10人乗りくらいの小さいボートで近づき、舳先から尖った岩場に飛び移り、そのまま3㍍ほどの岩壁をよじ登らないといけません。残念ながら、杖をついた方やハイヒールの方では難しいのです。
これらの情報は、旅行会社やパンフレット、観光協会などでも案内しているのですが、お客様の意識には残らない。そういったお客様が小笠原に来られてからイメージと現実とのギャップにガッカリされるのは、迎える私達も非常に残念です。このミスマッチを無くすため、マスコミに向けたPRよりも、お客様一人ひとりへの丁寧な説明はもちろん、旅行会社のツアー造成者やカウンター業務者、添乗員などへのレクチャーに力を入れています。「小笠原はリゾートじゃない」「南島ツアーは比較的ハード」「自分の足で歩かないといけない」ということを理解してもらい、ギャップを埋めるよう努めています。
≪旅館のサービスなど受け入れ体制の充実も≫
今後は、今実施している自然環境保全への取り組みを一層強化していくことと、その取り組みを知ってもらう活動により力を入れていきたいです。また、多様なニーズに対応できる受け入れ体制を作ることも考えています。宿のスタイルは、今までは、風呂・トイレ共同の相部屋が中心でしたが、これからは、風呂・トイレ付個室や、お客様が自由に組立てられる食事サービスの提供なども必要かもしれません。さらに、現在の小笠原観光は「歩く、動く」などのアクティビティ中心ですが、中高年層向けにあまり体力を使わずに周遊できるライトアクティビティも必要かもしれない。小笠原らしさはきちんと残しつつ、多様なニーズにもある程度応えられるよう、選択肢を増やしていければと考えています。