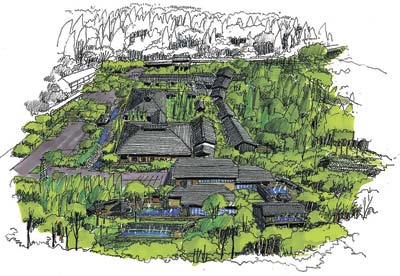山本峰子さん
山本峰子さん
山本峰子(ハンドルネーム)さんは、gooブログアクセスランキング100番台の人気ブロガー。“旅が大好きな温泉ソムリエ&フードアナリスト”が綴るブログ「コダワリ女のひとりごと」のアクセス数は1日当たりIP約2千、PV約1万(月間IP約6万、PV約35万)を誇り、企業の商品イベントや地域が主催するブロガーツアーにも多数招かれるなど、精力的に情報を発信している。人気ブロガーにブロガーツアーや観光地への率直な意見を聞いた。
【飯塚 小牧】
◇
――ブログを始められたのはいつですか。
8年前、2004年の夏からです。当時、仕事がIT関係だったので、仕事の一環として「今話題だから」と始めました。最初は、エッセイや小説のようなものを書いていて、人気はランキングで100番台に乗るぐらいありましたが、今ほど力を入れていたわけではありません。その後、5年前に札幌から東京に移り住んで、仕事を辞めてから本格的に始めました。企業のイベントに参加するようになったのは3年前で、ブロガーの招待ツアーは昨年から参加するようになりました。
――主催者は発信力を求めると思いますが、ブロガーの方々はどのようにイベントやツアーに参加されるのですか。
ホームページで募集している場合もありますし、ブロガーのプロダクションのようなものもあります。手法はさまざまですが、アクセス数などの条件があるので、応募して審査に通れば参加できます。私の場合は、固定の読者さんがいらっしゃるのでアクセス数は安定していますが、テレビなどで話題になったものはアクセスが急に上がったりします。このため、時事ネタを盛り込んでいるブログはアクセス数が多くなる傾向があります。
――ブログを拝見すると旅の記事も多いです。ブロガーツアーについてお聞かせ下さい。
もともと旅は好きなので、自分でもよく出掛けますが、ブロガーツアーは昨年、7回程参加しました。旅好きのブロガーにとっては、昨今の地域が主催するブロガーツアーはとても魅力的です。形態は地域によって違い、全額招待のツアーもあれば、「3万円を補助するので好きに周って下さい」というものもあります。もちろん、全額招待はうれしいですが、もし本当に旅好きのブロガーを集めたい場合は全額を出すのではなく、補助の方がいいかもしれません。私たちは一般消費者でマスコミではないので、旅が好きであれば、足がでるだけでも宿泊だけでも意欲がでて出掛けていきます。同じ予算なら単純に10人より20人呼んだ方が効果的ではないでしょうか。なかには謝礼が発生することで、旅にあまり関心がない参加者も見受けられるので、少し残念な気もします。また、せっかく予算をつけているのですから、記事以外にも参加者から意見を聞くなどフィードバックを求めるべきです。
――ご自身でもよく旅をされるそうですが、その際は何を参考になさいますか。
「どこかへ行こう」と思ったらまずインターネットで検索します。ガイドブックも買いますが、雑誌だと情報量が限られてしまいます。他の方のブログも参考にし、クチコミを見て調べます。ブログは画像が見られることが大きな魅力です。しかも、それはプロが撮っているわけではないので、偽りのない姿で信頼性があります。また、同じ場所に行っても視点はそれぞれ違うので、自分では気付かなかったところを他の人がクローズアップしているのを見るのは楽しいです。自分のブログでも、文章よりも画像を多く使い、写真で見せるようにしています。
――消費者目線で観光地に対する意見を教えて下さい。
全般的に言えることは、自分たちの魅力に気付いていないということです。とても珍しいものもPRしていない。青森に、日本でも数人しか持っていないウィーン菓子のマイスター資格を保有する方のお店があるのですが、地元の方はまったく知らないので「もったいない!」と思い、何度も紹介するうちに徐々に知名度が上がってきたという例もあります。地方ではブログの書き込み自体が少なく、発信力も低いので、埋もれてしまっているお店はとても多い。地元の人が売り出したいものと、来訪者のニーズが一致していないのかもしれません。食べ物などは、とくに東京から訪れる人は“おいしいもの”は求めていないと思います。東京で何でも食べられますから。それよりも、“珍しいもの”“新鮮なもの”を求めているので、無理に東京ナイズする必要はないですし、やはり郷土料理のようなものが歓迎されると思います。
――今後、ブログはどうなっていくと思いますか。
ブログがなくなるという人もいますが、私はなくならないと思います。Facebookも楽しいですが本名の人が多数なので、恐らく友人内の限られたものです。比較して、ブログは最初から不特定多数に発信するものなので、今後もブログの発信力には魅力があると考えています。
――ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・
【山本さんから宿や観光地へ一言】
「私は旅が大好きなので、ホテルや観光地紹介などのブログ記事投稿のお誘い大歓迎です!直接メールでご連絡下さい」。
山本峰子さん=メール(fuekitty@goo.jp )、BLOG( http://blog.goo.ne.jp/fuekitty )、Facebook( https://www.facebook.com/fuekitty )、Twitter( https://twitter.com/Fuekitty )。