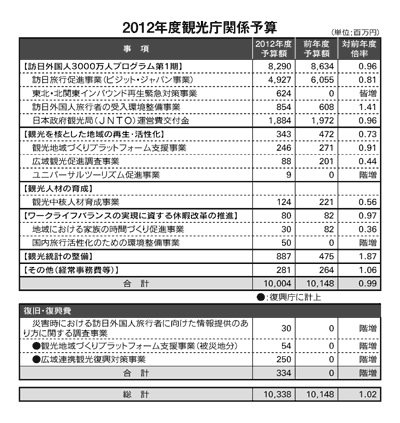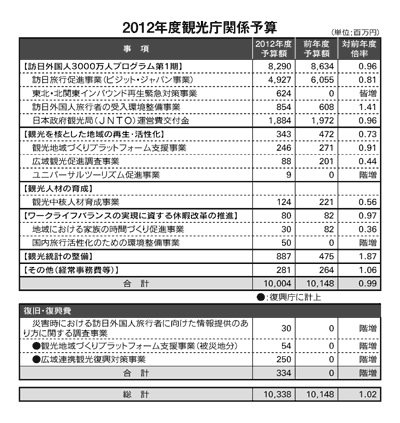
観光予算は103億円に――。昨年12月24日に2012年度政府予算案が閣議決定され、12年度の観光庁関係予算は11年度予算(101億4800万円)比2%増の103億3800万円となった。ただし、特別枠となる東日本大震災からの復旧・復興枠3億3400万円を除くと、前年比1%減の100億400万円。9月30日にまとめた概算要求では、11年度予算の8%増となる109億9100万円を要求したが、財源不足に悩む現状を受け、かろうじて前年並みを維持する厳しい予算となった。
【伊集院 悟】
事業別にみると、「訪日外国人3000万人プログラム第1期」事業は、前年度比4%減の82億9千万円。そのうち、中核となる訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパン事業)は、11年度に続き予算削減され前年度比19%減の49億2700万円となった。現地消費者向け事業は、中国・台湾・米国・香港に対し、KPI測定結果を踏まえた効果的な広告宣伝とメディア招請事業を行っていく。一方、韓国はKPI結果が有意義でないことを踏まえ他市場と同事業を取りやめ、個別で対策。安全・安心のメッセージを主要媒体やオピニオンリーダーなどを活用し、タイムリーに発信していく。
震災で大きく落ち込んだ東北6県と北関東3県(茨城・栃木・群馬)の訪日需要を回復するため、風評被害の払拭や観光振興のPRなどを行う東北・北関東インバウンド再生緊急対策事業には新しく6億2400万円を計上。それと連動し、訪日外国人旅行者の受入環境整備事業は前年度比41%増の8億5400万円となった。また、観光庁の溝畑宏長官が12月の会見で体制強化をうたっていた日本政府観光局(JNTO)の運営費交付金は、18億8400万円と、前年度比4%の削減となった。
観光地域づくりプラットフォームなど地域活性化へ取り組む「観光を核とした地域の再生・活性化」枠では前年度比27%減の3億4300万円。11年度予算で計上を見送られたユニバーサルツーリズム促進事業は、今回予算計上されるが、9月の概算要求より1千万円少ない900万円。
「観光人材の育成」枠は、前年度比44%減の1億2400万円と、大きく削減。「ワークライフバランスの実現に資する休暇改革の推進」枠は、同3%減の8千万円となった。
「日本再生重点化枠」で概算要求していた「国内旅行活性化のための環境整備事業」は「ワークライフバランスの実現に資する休暇改革の推進」枠内で5千万円計上され、「国立京都国際会館の整備・運営に係るPFI事業手法調査」は訪日外国人3000万人プログラム第1期事業内のMICE誘致・開催の推進で展開する効果測定に組み込まれた。一方、「日中国交正常化40周年記念少年招請事業」は外務省主導で行うことになり観光関連では未計上。1万人の外国人を日本に招き世界へ発信してもらう「Fly to Japan!事業」は、国の予算を個人の旅費に当てるのは難しいと予算計上されなかった。
12年度に本格調査を開始する「観光統計の整備」には概算要求よりも4200万円多く、前年度比87%増の8億8700万円となった。
また、東日本大震災からの「復旧・復興枠」では概算要求通り3億3400万円を計上。東北地方全体を観光の博覧会場に見立てる東北観光博(仮)など、東北地方への旅行需要回復と新たな観光地づくりのモデル構築をはかる「広域連携観光復興対策事業」は2億5千万円を盛り込んだ。「災害時における訪日外国人旅行者に向けた情報提供のあり方に関する調査事業」は3千万円。被災地向けに条件を緩和した「観光地域づくりプラットフォーム支援事業(被災地分)」は5400万円となった。