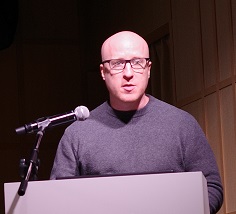2025年2月9日(日) 配信
.png) 会場の海軍記念館(海上自衛隊舞鶴地方総監部)
会場の海軍記念館(海上自衛隊舞鶴地方総監部)
暮れも近い12月中旬、久々に京都府舞鶴市を訪ねる機会を得た。日本遺産・鎮守府4市(横須賀・呉・佐世保・舞鶴)が毎年持ち回りで開催するシンポジウムである。
日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じた日本の文化・伝統を語るストーリーを認定し、これらの活用による地域活性化をはかる制度である(文化庁)。従って、事業を担うのは、主に文化財や歴史など文化や観光系の関係者である。
しかし鎮守府4市では、これらの活動と並行して、5年前から大学や高専の建築・土木・機械などの分野の学者による研究と発表会を重ねてきた。テーマは「理系で読み解く日本遺産」。発案者は前舞鶴市長で旧運港市日本遺産活用推進協議会会長(当時)の多々見良三氏である。
4市にある日本遺産の構成資産の多くは、旧鎮守府の司令長官官舎や煉瓦倉庫、ドック跡、防空指揮所などの地下壕、砲台跡、旧水道施設など歴史的建造物が多い。これらを生かすには、その構造とともに強度、建築材料などの解析が不可欠である。これらに携わるのは技術者や大学などの研究者であり、それが「理系で読み解く」である。
会場は、海上自衛隊舞鶴地方総監部にある「海軍記念館講堂」。午前中は、4市7人の研究者による研究成果の発表と討議、午後からは一般市民向けのシンポジウムが開催された。
舞鶴は、北吸地区にある赤煉瓦倉庫12棟(うち8棟は重要文化財)、いわゆる「赤れんがパーク」が2012(平成24)年にオープンし、現在の観光拠点の一つになっている。21(令和3)年からは、民間活力によるPFI事業により新たな活用事業もスタートした。このなかで、まだ未着手の6号棟から8号棟(文部科学省所管)には、もともとあった赤煉瓦博物館(1号棟)の移設も含めた、新たな活用構想も検討されている。
 舞鶴湾洋上に浮かぶガソリン庫「蛇島」
舞鶴湾洋上に浮かぶガソリン庫「蛇島」
さらに20(令和2)年には、湾内でかつてガソリン庫として活用された「蛇島」が、日本遺産の構成文化財として追加認定され、その保全と活用が検討されている。蛇島は、周囲650㍍の無人島だが、中世には洋上に浮かぶ山城があり、舞鶴湾防衛の要衝の島である。その島を貫く4本のトンネルがガソリン庫となっていた。ガソリン庫ということは、かつてこの湾から洋上飛行機も飛んでいたことを意味するが、今後の活用にも大いに参考になる。
舞鶴はじめ鎮守府4市では、これまでにも4市のガイドが他市の紹介もできるような研修を積むガイド交流や、日本遺産ストーリーに因む物産開発と4市での同時販売、各湾にある民間クルーズ会社による「クルーズサミット」と相互交流など、4市一体で運営できる体制整備も進めている。
遠く離れた4県にまたがる日本遺産をどのように生かすか。学術交流をはじめ、そのモデルとなる事業化に期待したい。
(観光未来プランナー 丁野 朗)
、城戸陽二妙高市長.jpg)
室伏広治スポーツ庁長官、都倉俊一文化庁長官、秡川直也観光庁長官が署名した.jpg)

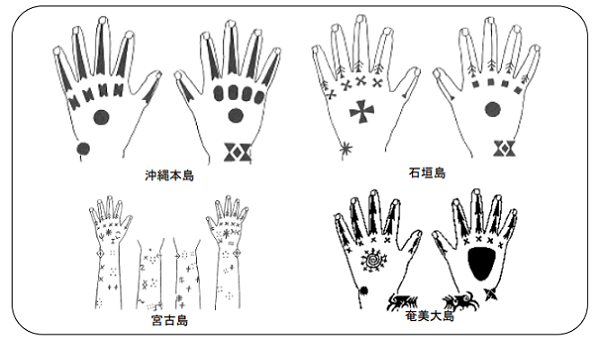

.png)