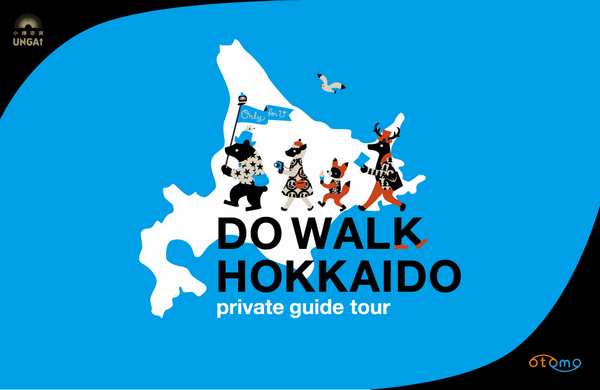2023年4月22日(土) 配信
 品川の歴史に触れる
品川の歴史に触れる
しながわ観光協会と八芳園、船清は3月11日(土)、「しながわ歴史文化体験モニターツアー」を行った。
しながわエリアの歴史や文化に触れ、屋形船に乗船しながら地産地消の食を味わうツアーで、観光資源の磨き上げを目的に実施。参加者は江戸時代から続く八芳園の日本庭園や旧東海道品川宿のまち並み散策の、屋形船での特別なランチを楽しんだ。
江戸時代の品川は水が豊かで、野菜や茶の栽培が行われ、遠浅の品川浦では漁も盛んだった場所。ツアーのスタート場所となった八芳園の庭園は江戸時代、徳川家康の家臣大久保彦左衛門の屋敷だった場所で、大正時代に実業家の久原房之助によって今の庭園の基礎が整えられた。庭園内には「大護神社」や茶室「霞峰庵」、「夢庵」などさまざまな見どころが点在している。
 虚空蔵横丁の煉瓦塀
虚空蔵横丁の煉瓦塀
庭園散策の後は、1187年に源頼朝が安房国の洲崎明神を勧請したことが始まりといわれる社で、徳川家康が関ケ原の戦いに際し戦勝を祈願した場所でもある品川神社や、金運上昇のご利益がある阿那稲荷神社などを参拝。鯨塚や品川台場(御殿山下砲台跡)、虚空蔵横丁の煉瓦塀を巡り、品川の歴史に触れた。
 船清の伊東陽子女将がガイド役に
船清の伊東陽子女将がガイド役に
ツアーの最後は、品川の食の魅力に触れる時間として、揚げ立ての天ぷらやアサリの浸し飯など船清伝統の会席料理に、東京湾近郊で水揚げされたスズキと品川海苔のカルトッチョなど八芳園がプロデュースした品川エリアを中心とした東京の地産地消食材を使用した洋食を組み合わせた特別なコース料理を提供した。
また船内では、船清の伊東陽子女将が品川エリアの最近の話題や歴史、食材の魅力などをクイズを交えながら紹介し、参加者を楽しませた。
 東京湾近郊で水揚げされたスズキをカルトッチョに
東京湾近郊で水揚げされたスズキをカルトッチョに
昨年3月に品川区の事業として、しながわ観光協会が行った取り組みを発展させ企画された今回のモニターツアー。
3月の事業はまん延防止等重点措置に伴い、屋形船の通常営業ができなかった船清の屋形船の中で、同じく同措置により地域や自治体のプロモーション強化が進む八芳園の料理を楽しんでもらおうと企画された。
同協会はこの企画にまち歩きの要素を加え、持続可能性もテーマに組み込み、東京観光財団の地域資源発掘型プログラム「動く料亭~屋形船に乗るサステナブルな日本文化体験ツアー」事業の一環として八芳園と船清協力のもとツアーを企画、日本旅行がツアーを実施した。
 東京の紅茶などでつくるプリン
東京の紅茶などでつくるプリン
八芳園と船清はこれまでも、東京都や東京観光財団が指定した9つの東京ビジネスイベンツ先進エリアのひとつである「DMO GATEWAY 新品川」として、ビジネス利用の訪日客向けに新品川エリア(品川・田町・芝・高輪・白金・港南)でのイベントや宿泊施設への誘致・紹介を行ってきた。
船清が守り続ける屋形船文化と、八芳園とともに開発した地産地消の食材を使用したクルーズメニューを通して、品川の水辺観光振興を目指す新たな共創価値を創造・発信したいという思いを込めた八芳園。執行役員の窪田理恵子氏はツアーを振り返り、「エリアで連携したことで、単独では実現できない観光の磨き上げの一歩を踏み出すことができた。
伝統や文化だけでなく、『サステナブル』というキーワードを盛り込むことで、参加者の皆様に楽しみながら社会や未来への問い掛けもできたのではないでしょうか」とモニターツアーを総括した。「今後もさまざまな観光コンテンツを共創しながら磨き上げることで地域を盛り上げ、25年の高輪ゲートウェイシティ(仮称)開業時には魅力あるコンテンツを創り上げエリアでのMICE誘致をはかりたい」と今後の展望を語った。
品川は水辺と共に発展してきたまちなので、屋形船は欠かせない存在と語る伊東女将は、「屋形船を楽しむ目的で品川に来る人に、より深く歴史や文化、魅力を知っていただきたいと思い続けていたので、今回のモニターツアーそのための一歩になったのではないか」と手応えを語った。
その一方で自走化するための課題に「価格」を挙げ、「地産地消の食材となると時期が限られてしまううえに、食材費も通常より高くなるので、ツアー価格もそれに応じて高額にならざるを得ないと思う。品川の魅力をより多くの人に感じてもらうためには、例えばまち歩きと料理の提供はせずガイドを聞きながら屋形船で東京港を周遊するコースのように、コンテンツを1つに絞り、気軽に参加しやすくすることが必要ではないか」と課題感を示した。