2023年2月14日(火)配信

JTB(山北栄二郎社長)は2月3日(金)、東京都品川区の本社ビルで6月以降出発の海外旅行商品の販売を発表した。コロナ禍以降、海外旅行商品の販売を本格的に展開するのは3年ぶり。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年から海外募集型企画旅行の催行を中止していたが、22年4月のハワイ方面の再開を皮切りに順次拡大。10月の水際制限の緩和以降、海外旅行への機運が高まりつつある環境を踏まえ、今回の本格再開に至った。
代表取締役専務執行役員ツーリズム事業本部長の花坂隆之氏は「水際対策緩和や、10月の全世界の感染症危険情報のレベル1への引き下げなどを受けて、お客様の申し込みが着実に回復してきている。旅行の需要が戻りつつある」と語った。
続けて、コロナ禍を経て、利用者や環境の変化について「お客様の旅行ニーズの多様化、パーソナライズ化の加速、Web申し込みへのシフトなど、お客様の購買行動の変化がより一層進んでいる。一方、航空やホテルについては、グローバル化への進展により、代金のダイナミックプライシング化が進んでいる」と話した。
このような変化に対応すべく、JTBの23年度海外旅行商品は、①「お客様実感価値」の向上②サステナビリティ/SDGsへの取り組み③「安心・安全」の取り組み継続――の3点を中心に進めていくと述べた。
ニーズの変化に合わせて、ホテル・航空券を自由に選択し、希望に合ったツアーに設定を変更できる「ルックJTBMySTYLE」を提案。旅行の目的や参加形態に応じて、個別にコンサルティングしたサービスパッケージを展開する。
約3年ぶりの海外旅行自体に不安を感じる利用者向けに、旅行前から帰国後まで一気通貫のサポート体制を整えた添乗員同行商品も強化。少人数でのツアー設定やワンランク上の上質なプラン、体験型プランなど、添乗員付き商品ならではの特別企画も展開していく。
商品を通じて、サステナビリティやSDGsへの貢献にも取り組む。旅行日程表のWeb化によるペーパーレスの試みや、公共交通機関を使用したCO2削減を意識したツアーを設定した。
安心・安全の取り組みとしては、JTBの最大の強みである海外ネットワークを活用したサポート体制の再構築や、独自の補償プランの設定、デジタルを活用した利用者とのコミュニケーションを強化する方針だ。
そのほか、海外旅行の機運醸成をはかり、2月4日(土)から海外旅行のテレビCMを放映。約3年ぶりのリアル形式での海外旅行相談会の開催や、羽田空港と協業した「海外旅行の添乗員と楽しく過ごす」日帰りバスツアーを実施すると発表した。



塚島英太次期部長予定者、菅義偉前首相、星永重部長、石井浩郎国交副大臣、多田計介全旅連会長-WEB.jpg)








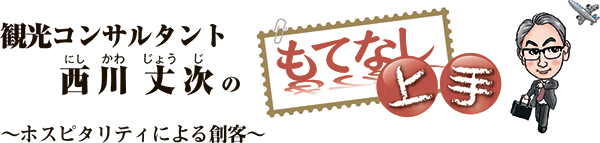
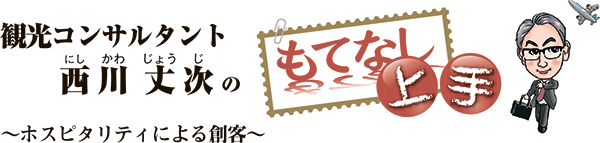


ホセ・マリアイセガBCC学長、荒井奈良県知事、ズラブ・ポロリカシュヴィリUNWTO事務局長、石井副大臣-コピー.jpg)


本保代表、荒井奈良県知事、サンドラ・カルバオ部門長、ホセ・マリアイセガBCC学長.png)

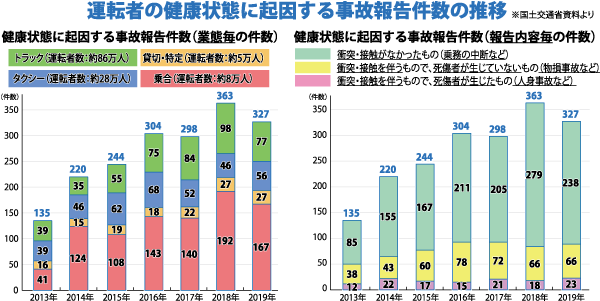
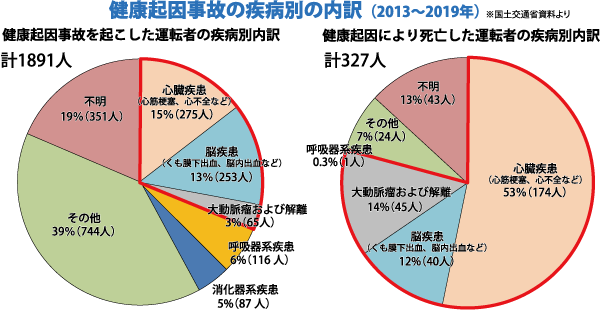

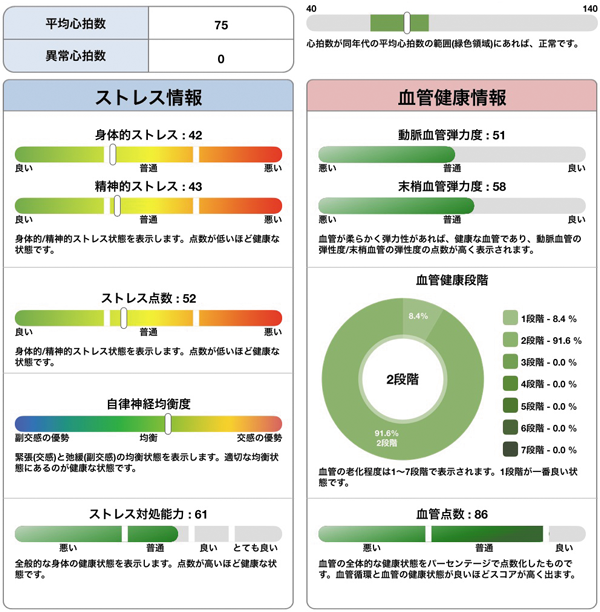
 03-5809-3938
03-5809-3938_000001-2.jpg)