2023年2月10日(金) 配信

岐阜県・白川村は昨年12月、村単独では初となるファムトリップを実施した。
世界遺産集落に集中する観光客によるさまざまな課題解決に向け、同村は公共交通機関でストレスを感じることなく移動可能な、飛騨地域の周遊ツアー造成を進めている。ファムツアーでは村の食文化と合掌造り集落を守り抜いてきた人々の思いを中心に、村の観光の在り方を模索。メディア関係者や現地ガイドとの意見交換を行った。
合掌造り集落で有名な白川村は、魅力的な食文化に出会えるまちでもある。冬の間雪に閉ざされるこの村では大豆が貴重なたんぱく源となり、「すったて汁」や「石豆腐」といった郷土料理が祝いの席や報恩講(浄土真宗開祖の親鸞聖人の祥月命日の前後に営まれる法要)などのハレの場で親しまれてきたという。
「すったて汁」は、茹でた大豆をすり鉢や石臼などですりつぶした「すったて」に、濃い味噌汁を加えた汁物。具材は入っておらず、シチューのような味わいと、口の中に広がる大豆の香りが食欲を掻き立てる。
村ではこの「すったて汁」を地元食材と掛け合わせ鍋料理にアレンジ、2014年に開かれた「ニッポン全国鍋グランプリ」に出場しグランプリを獲得した。

ファムトリップでは「ます園文助」でこのすったて鍋を味わった。同店ではこのほかに、湧水を利用して育てたイワナやアマゴ、ニジマスを味わうことができる。
一方の石豆腐は、貴重なたんぱく源として日持ちさせるため水分を極力抜いた豆腐で、荒縄で縛っても崩れないほどの固さに仕上がっている。ファムトリップで訪れた「深山豆富店」は2021年3月に後継者がいないことなどから一度閉店したが、ヒダカラ(岐阜県飛騨市)が事業継承するカタチで再オープン。
同店では白川村の湧き水と天然にがり、国産大豆を原料とし、ぎっしり詰まった大豆の味と香りをしっかりと堪能することができる「石豆腐」をはじめ、すったてやこも豆腐、豆腐に合う調味料などが購入できる。また店内では、同店おすすめの「豆腐ステーキ」などさまざまな豆腐料理のレシピを配布している。

店主の古田智也氏は「ほかの豆腐にはない固さと、凝縮して固くすることで感じられるしっかりとした豆の味が魅力」と語り、「残していかなければならない財産」と力を込める。
郷土食に加え白川村では17年から合掌造り住宅を活用した食の体験「遠山家家ごはん」を展開している。重要文化財「旧遠山家住宅」の座敷で地元の食をふんだんに使った「遠山家家ごはん」が味わえる企画で、提供される弁当は村内の老舗旅館「御母衣旅館」と人気飲食店「お食事処次平」が特別に考案。提供時には「村人のもてなしの心」を少しでも感じてもらえるよう、祝い事や仏事の際のごちそうのもてなしに使われた「高膳」で提供する。
□村を核に観光客を飛騨地域に分散
今回のファムツアーは、観光庁・環境省「持続可能な観光コンテンツ強化事業」の支援を受け実施された。観光客が公共交通機関を使いスムーズに移動できる飛騨地域周遊の旅行商品を造成するにあたっての意見を収集し、旅行商品としてブラッシュアップしていくことが狙い。
19年、過去最高の約215万人の観光入込みを記録した白川村。一方で奥深い山峡の村で鉄道の駅がないため、移動が車両に限られてしまい、駐車スペースの不足という問題が発生。繁忙期となるゴールデンウイークやお盆、シルバーウイーク、紅葉シーズンなどは、白川郷ICを超え高速道路まで続く駐車場待ちの車による渋滞が問題になっている。また、村内観光に利用できる2次交通が整っていないため、金沢や高山などから高速バスで村を訪れた人の滞在先が世界遺産集落に集中してしまっている。
こうした問題を解決するべく白川村は、村を核に周辺の高山市や飛騨市の個人では訪れ難い魅力ある観光スポットを巡る周遊プランの造成を進めている。観光振興課観光担当の小瀬智之課長補佐は「白川村が含まれる飛騨地方は、独自の文化と伝統、豊かな自然をベースとした魅力ある観光スポットが点在していますが、公共交通機関でのスムーズな移動が難しい地域でもあります。周遊プランでは、公共交通機関を使うケースが多い外国人観光客やシニア層の小―中規模のグループをターゲットに、訪れる人が公共交通機関を利用して移動する際ストレスを感じることなく観光を楽しめるような行程を組んでいきます」と構想を説明。「これによって、地域の観光の相乗効果を生みだしたい」と力を込める。
これに加え小瀬氏は村のサステナブルツーリズムの在り方にも触れた。「白川村は結による屋根の葺き替えや、合掌造り家屋の保存活動など、既にサステナブルな取り組みを実装しているので、訪れる方には集落での観光を楽しむとともに、保存活動などへの理解を深めてもらうことも、サステナブルツーリズムのひとつになる。一方、サステナブルツーリズムを推進しすぎることで、住民負担が増す状況は避けなければなりません。無理のない範囲で、サステナブルツーリズムを白川村流に展開するのが理想です」と強調した。
事業目的を実現するための効果検証の助言などを行う十六総合研究所飛騨國サテライトリサーチ部の研究員、森俊介氏は白川村の観光の魅力と可能性を「合掌造り家屋の成り立ちから、そこでの人々の暮らしや経済活動、そして昨今の保存活動に至るまで、『持続可能な生活』が営まれ続けられてきたこと」と説明。「現代における持続可能性を考えるうえで、『リビングヘリテージ』としてこのことを伝え続けることが重要となる」と自身の考えを述べた。
そのうえで、「人口減少問題をはじめとしたさまざまな課題を抱える飛騨地域は『課題先進地』と呼ばれ、今後の日本の未来を考えるうえで、非常に重要な地域であると認識しています。今後も白川村が持続可能な村であり続けられるよう、伴走していく」と語った。

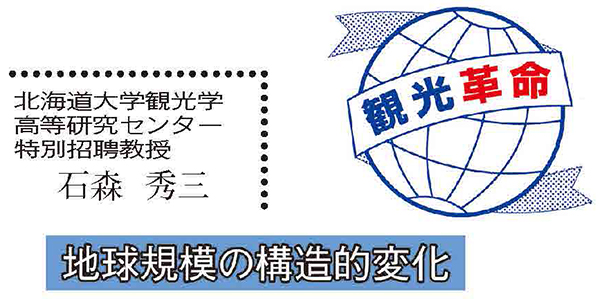
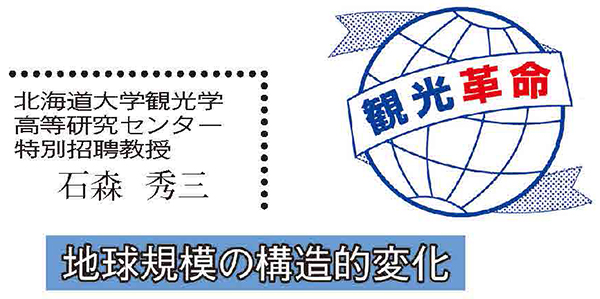

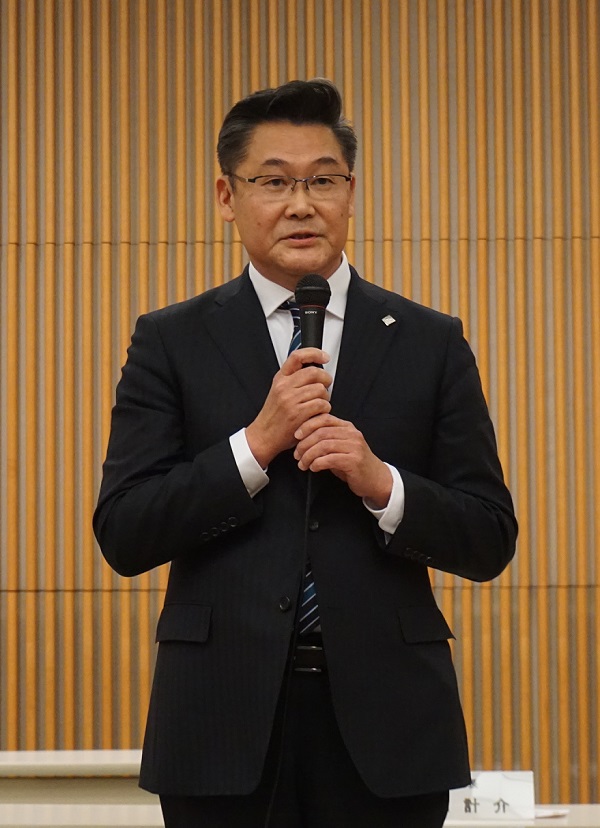



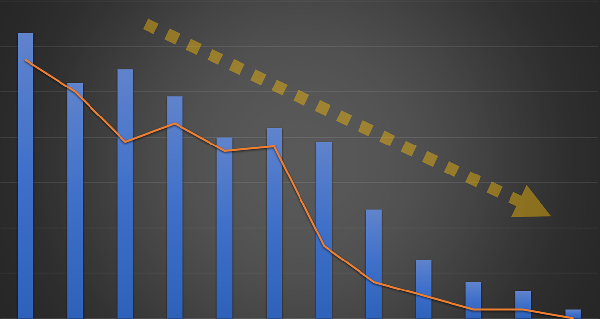
と福井県の白嵜淳首都圏統括監.jpg)



