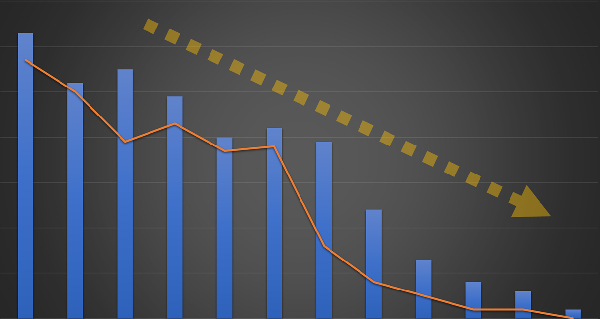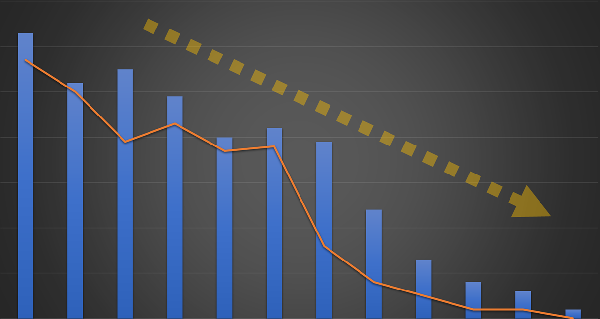2023年3月4日(土) 配信

近年駅のプラットフォームで流される発車(閉扉)前の警報音が以前の発車ベル、ブザーなどから急速に“メロディー”(発車テーマ音楽ともいうべきか)に変わりつつある。
先日、出先で友人危篤の報に接し、某鉄道で急きょ病院に急ぐ途中、長い待ち時間の末に、ようやく来た電車に乗車した。さらに長い停車時間の後、ようやくドア閉扉を知らせる“メロディー”が流れ、その音楽の悠長な調べに苛立った思いをした経験がある。
何でも安全上、乗客に慌てず、焦らず乗車してもらうため、落ち着いた“メロディー”を流しているとのことであったが、“音楽”を聞いて苛立った思いをしたのは初めてのほろ苦い経験であった。
そういえば、東北新幹線開業の際、筆者は国鉄の営業担当者だったが、試乗会の折、ある評論家から「開業後に、車内放送で駅停車の案内をする際、民謡の宝庫である東北に相応しい、各駅の所在地の民謡をテーマ音楽として流してはどうだろうか」との提案を受けた。
早速、関係地域の代表的な民謡を地元から推薦してもらい、これを停車案内前のテーマ音楽として車内で放送した。その結果、地元の方々には歓迎していただき、「ふるさと」が近づく実感が湧いてきて、「感慨無量」だったなどの好評を得た。
しかし、そのほかの乗客の声や一部の投書では、「列車内の落ち着いた雰囲気が壊れる」とか、「現代の鉄道(新幹線)に昔の民謡は、相応しくない」などの意見も寄せられたため、間もなく、民謡を車内放送のテーマとすることは止めて、チャイムのみとした記憶がある。
考えてみると音楽(少なくともメロディー)は作曲者ないし、撰曲者の音楽に寄せるこころないしは、興趣を反映して選ばれるものであるだけに、聞く人にとっては、曲が好き嫌いの対象となることは否定することができない。
しかし、駅のホームで流される音楽は本来ドア閉扉を乗客に告げ、速やかな乗車を促すものであり、安全に関わる警報音でもある。
従って、乗客には「閉扉近し」という情報を伝えることに徹した、いわば好き嫌いの対象外となる「音」(音楽ではなく)に徹する必要がある。
駅ホームの「音」は聞く人に辛かった過去を思い出させたり、旅行の楽しい思い出を蘇らせるなどの効果のある“音楽”とは異次元の「音」に徹することが、必要なのではなかろうか。
安全第一の見地から私見としてホームで流される音は音質と音量、鳴動時間、などを駅の実情に応じて、調整のうえ、ベルやブザーなどの単純な音に、徹するべきであると思う。
ホームでの待ち時間に名曲の一部のような音楽を流すことよりも、待ち時間が少なくなるダイヤ面での工夫こそ、真のサービスではないだろうか。
 須田 寛 氏
須田 寛 氏
日本商工会議所 観光専門委員会 委員
須田 寬 氏








⇒札幌(丘珠).jpg)
⇒名古屋(小牧).jpg)