「トラベルスクエア」「立国」の裏側にはリスク
2019年8月19日(月) 配信
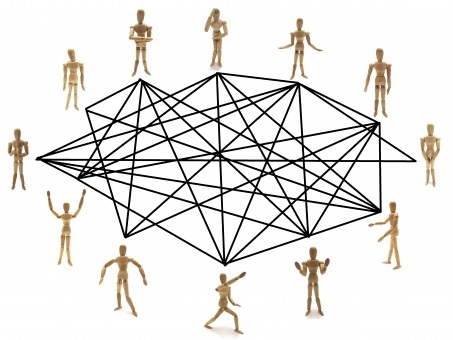
1980年代半ば、月刊ホテル旅館の編集長を務めていたが、企画の中に全旅連青年部長をホストとする対談シリーズを設けていた。時の部長さんに会ってみたい人を挙げてもらって、編集部が斡旋してシリーズ化したものだ。その1人にNECの関本忠弘社長がいた。PC―8800シリーズを発表し、「電子立国」の立役者ともてはやされていた絶頂期だったと思う。
対談の過程で「電子立国は追い風ですね」という質問をしたのだが、関本社長の眼差しがぐっと厳しくなったのを今でも鮮明に覚えている。関本社長は「立国なんてものに頼っちゃダメなんだ。もしも、それが倒れてしまったら、何も残らないじゃないか! 経営者はそういう甘い言葉を警戒しなきゃ」と語ってくれた。1つの業務部門に偏れば、成長の速度は早まるかもしれないが、それだけリスクも背負う、という教えだ。
そんなことがあったから、僕には観光立国という言葉に終始違和感を抱き続けていた。調べてもらって構わないが、僕自身は観光立国でインバウンド客を無批判に無限抱擁的に受け入れることには一貫して慎重な論陣を張ってきたつもりだ。インバウンド集客が生命線になったら、かえって相手国の経済社会状況の変化に身を任せてしまうカントリーリスクが怖い。
今、日韓の問題で、韓国からの集客に翳りが出始めていると聞く。官房長官の菅さんが、記者の韓国からのインバウンド客減少についての質問に、鼻しらんだように「もともと、そういう風に集客の源を一本化していく方が悪い。経営とはもっと多様な客を相手にしなきゃ。例えば、他の国々からの集客を強化するとか」と答弁していたのが印象的だった。
ぶっきら棒な言い方に、反発を覚えた旅館経営者の方々も多いと思われるが、ここは菅さんの言い分の妥当性をとりたい。
僕の取材領域はコンビニからナイトクラブまでさまざま領域にわたっていたが、その経験から割り出された経営の「真実」の1つは、「商売はなるべく商圏を狭くして、そこから反復来店してくださる。そういう姿が美しい」というものだ。
さすがに観光は隣近所数キロ圏内を相手に、というのではビジネスにならないが、少なくとも自分の県と両隣の県あたりが発地の常連さんが多いと経営は安定する。顔を知っているお客こそが、例えば震災などの難局でも一番頼りになるものだろう。国外客はもちろん大事だが、なにかあったときの支えにならない。いつだって、「遠い」のは旅をやめる動機の最大のものだからだ。
「立国」という言葉の勢いに負けず、なるべく狭い商圏で商売が成立するように考える。それを経営の原点としたい。
コラムニスト紹介

オフィス アト・ランダム 代表 松坂 健 氏
1949年東京・浅草生まれ。1971年、74年にそれぞれ慶應義塾大学の法学部・文学部を卒業。柴田書店入社、月刊食堂副編集長を経て、84年から93年まで月刊ホテル旅館編集長。01年~03年長崎国際大学、03年~15年西武文理大学教授。16年~19年3月まで跡見学園女子大学教授。著書に『ホスピタリティ進化論』など。ミステリ評論も継続中。
